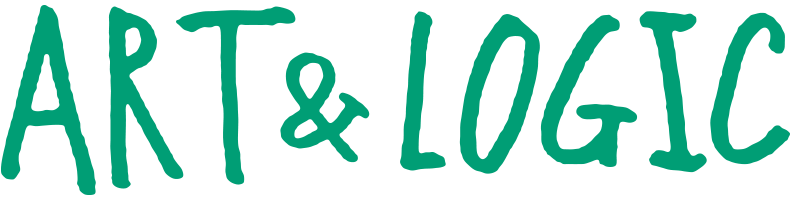経営者はなぜ美術館を創るのか?
日本を代表する企業において美術館を有しているところは決して少なくはない。
著名なところではアーティゾン美術館(旧ブリヂストン美術館)、出光美術館、サントリー美術館などである。
美術館を運営するのは多大なコストと労力を要し並大抵のことではない。
美術館を運営するためには展示スペースはもちろんのこと、美術作品を収蔵するための収蔵庫が必要である。
この収蔵庫も単なる倉庫だと美術作品が経年劣化し傷んでしまうので温度や湿度などの徹底した空調管理を施さなければならない。
また、美術館にはキューレーター(学芸員)をはじめとする常勤のスタッフも置かなければならないので、生半可な気持ちでは決して運営が出来ないのである。
なぜこのような労を惜しんでまで経営者たちは美術館を所有、運営するのであろうか、それはアート(芸術)と経営が実は密接に関係しているからではなかろうか?
アートと事業経営はまったく相容れないものであると思いがちであるが実は多くの共通点がある
その共通点とは、
(1)世の中にない全く新しい価値を生み出すこと。
画家は真っ白なキャンバスに常に絵筆で新たな自己表現をする。
エポックメイキングな企業は今までにない新たな価値を創造する。
それは何も描かれていないキャンバスに常にあらたな作品を創造するアーティストのスタンスととても似ている。
現在のエスタブリッシュメントカンパニーの多くは戦後の焼け野原、つまりゼロの状態からイチを生み出した。
ちなみに本田宗一郎がホンダ(本田技研工業)を設立する前、彼は自転車に海軍からの払い下げのエンジンを積んで今でいう原付バイクを発明した。
この時の会社名はアート商会であるのだ。
(2)調和とバランス
優れた芸術作品は絶妙な調和とバランスで構成されている。
例えば印象派の巨匠セザンヌやモネの絵の多くは背景である自然と人物との織りなすハーモニーがたいへん素晴らしい。
これは事業経営においても経営者と従業員など周辺のリソースとの関係性にとてもよく似ている。
ブリヂストンの創業者、石橋正二郎がブリヂストン美術館(現、アーティゾン美術館)を創設した主旨は、多くの国民がアートに接することで心が豊かになり人生を謳歌してもらいたいと願ったことであるのだ。
(3)時代を読み取る力、新たな挑戦をし続ける姿勢
優れたアーティスト(芸術家)は常に時代を読み取り作品に反映をさせている。
現代アートの巨匠アンディーウォーホルは大量消費文化の象徴としてキャンベルのスープ缶やマリリンモンローなどの誰もが知っているモノやコトをモチーフに作品を制作した。
つまり彼は世界一の消費国家、アメリカの空気を読み取りアートを大衆にデリバリーしたのである。
どんなに良いサービス、商品でもその置かれた時代の空気を読み取り時代に合うように昇華していかなければ人々の心は掴めまい。
また、イギリスを代表するアーティスト、デビッド・ホックニーは2023年11月現在86歳と高齢ながら、27年ぶりに日本で開催された個展では最新鋭のiPad(アイパッド)を駆使したさまざまな作品が展示されていた。
これを彼はデジタル・ドローイングと名付けたのだ。
アートと経営、どちらも高度な次元のクリエイティビティーが要求されるのだ。